手のひらを身体全体と捉える考え方があります。
いろーいろな考え方があって、その色々を見ていると迷うばかりです。
赤ちゃんを見ていると、脳と手の発達はとても重複しているなあと感心します。
手を動かすことと、脳を働かせることが連動しているのですよね。
これは脳の図で有名な脳の中のこびと(ホムンクルス)からもよくわかります。

ヒトの一次運動野における体部位局在の地図 (脳の中のこびと(ホムンクルス)http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/32/index-32.html より)
手の部位って広いですねえ。
そして顔も大きい。
ここから派生して細かく考えていくこともあるのでしょうが、
実際はいろいろな要素が組み合わさり、なかなか難しいです。
東洋医学の世界でも、手を、身体全体と診立てたり、頭と診立てたり、背骨を中心にみたてたりと、悩ましいです。 さて、これは手の甲置き鍼を貼っています。
さて、これは手の甲置き鍼を貼っています。
この考え方、いろいろあるのです。
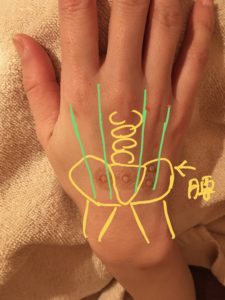
イラスト
この考え方は、手の甲を腰と診立てて、腰の痛みに対応していると考えられます。
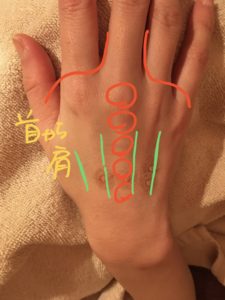 こちらの考え方は、手の甲を首から肩とみたてて、首の寝違えで反応を診立てています。
こちらの考え方は、手の甲を首から肩とみたてて、首の寝違えで反応を診立てています。
面白いですよね
同じ反応でも、どう考えるかはさまざまなのです。
そしてこれは実際には寝違えの方への施術でした。
寝違えには落枕という有名なツボがあります。
このツボも手の甲ですが、特効穴的に考えることもできますし、
こうやって反応を探して、結果的に落枕というツボに行き当たることもあります。
まあ、どっちにしろ、効けばOKなのですが、
東洋医学の臨床の場であるのならば、最低限、どんな理論があり、何をつかっているのかというあたりは踏まえて、経穴を使っていきたいなって思います(^^)
うふふ。
