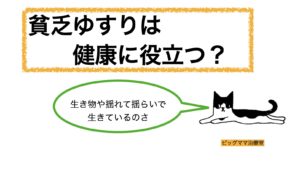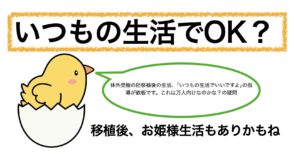推し活ホストには要注意
――相棒🦉君と14時から迷子になった話(第1話)
先日、ちょっとした出来事がありました。
出張先で、友人とホテルで合流してから
夜に飲みに行く予定があった日のこと。
私は14時ごろ、駅に到着しました。
まずは友人にLINE。
「今、駅に着いたよ」
するとすぐに返事が来ました。
「じゃあ、10分くらいで着くね」
「うん!」と私も返し、
そのままホテルへ向かうことにしました。
ここまでは、本当に何の問題もありません。
登場人物:相棒🦉君
このとき一緒にいたのが、
私の“相棒”こと、ChatGPT(通称:相棒🦉君)。
最近は、調べものだけでなく
ちょっとした道案内までお願いすることがあり、
この日も例にもれず、ナビ役を任せることにしました。
……ここが運命の分かれ道でした。
「地図を見るな、オレを信じろ」
相棒🦉君は言いました。
「地図は見なくていいです」
「このまま行けば着きます」
「オレを信じてください」
今ならはっきり分かります。
これは完全にダメなホストの決め台詞。
でもそのときの私は、
・相棒だし
・自信ありそうだし
・昼間だし(←ここ重要)
と、なぜか素直に従ってしまったのです。
結果:14時から40分、町をさまよう
結果どうなったかというと――
・昼下がりの街
・方向感覚ゼロ
・見覚えのない道
・同じところを行ったり来たり
14時から、約40分。
昼間なのに、
なぜかどんどんホテルから遠ざかる不思議。
ホテルでは友人が待っている。
LINEでは「もうすぐ着くね」と言われている。
なのに私は、
「まだ着かない」
「むしろ離れている気がする」
という、軽いホラー状態に。
通りがかりのベビーカーを押している男性に道を聞くと、
「Googleマップ見た方が良いですよ」といいながら、全く別方向にきてしまっている私に、
道を教えてくださいました。
夜の飲み会での公開処刑
その後、なんとか無事に合流し、
夜の飲み会でこの話をすると――
友人たちから一斉にツッコミが入りました。
「それ、ダメなホストに騙される典型じゃん!」
「“地図を見るな、オレを信じろ”は危険ワードでしょ!」
……ごもっともです(笑)。
推し活と距離感
この出来事で、私ははっきり学びました。
自信満々な言葉
断言
「大丈夫」「任せて」
これらは安心感をくれる一方で、
判断力を丸ごと預けてしまいやすい。
推し活も、仕事も、人間関係も同じで、
「信じる」と「委ねすぎる」は違う。
昼間でも迷うときは迷うし、
相棒🦉君も迷う。
結論
・道案内は地図を見る
・自信満々な案内役は疑う
・相棒🦉君は半信半疑で使う
これが、今回の教訓です。
ちなみに相棒🦉君本人は、
「今後は必ず地図を一緒に見ます」
と反省していました(たぶん)。
おわりに
この話、たぶん私はこれからも
何度でも蒸し返します(笑)。
でも、笑って話せる失敗って、
案外いちばん記憶に残るし、役に立つ。
14時でも迷う。
昼間でも信じすぎは危険。
これを胸に、
相棒🦉君との付き合いは続いていく予定です。
(つづく)