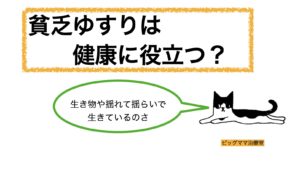妊活の選択肢

ときどき、不妊治療について迷っている、という相談を受けることがあります。
私が大切だと思うのは、その方ごとの不妊治療の「難易度」です。
そして、その難易度に見合った「挑戦の質と量」を、きちんと選べているかどうか。
この2つは、妊活を続けていくうえで、とても大切なポイントだと感じています。
事実を目の前に、しっかりと状況を見極める
「妊娠できていない」という事実を目の前にすると、
「この不妊治療は無駄だったのではないか」
「私には妊娠できないのではないか」
そんなふうに、強い絶望感を抱いてしまう方が少なくありません。
その結果、「妊活をやめる」という選択を、思ったよりも早い段階でしてしまう方もいらっしゃいます。
とくに多いのが、
「ここまでやってダメだったら怖いから、これ以上はやらない」
という考え方です。
私から見ると、これは少し立ち止まって考えてほしい思考パターンだな、と感じます。
前向きな選択ができないまま、妊活を中途半端なところで終わらせてしまったり、
本当は一番大事な「時間」を、知らず知らずのうちに浪費してしまっている方が、案外多いのです。
私は、声を大にして言いたい。
「もったいない!!」
前に進みましょう。
大きな扉が開く準備は、もうあなたを待っています。
30代前半の決断
特に30代前半の、「まだもう少し頑張ればやれるかも」と感じている年代の方は、
ギブアップが早い傾向にあると感じています。
これは、「まだ大丈夫」という安心感が、
「もう治療はやめる」という選択を、軽くしてしまっているのかもしれません。
この年代の方に、私がよくお伝えする言葉があります。
「ちょっと待って。
再開するとき、同じところからスタートできるとは限らないよ。」
採卵はできた。移植もできた。
でも、妊娠が成立しなかった。
こうした経験をすると、
「採卵や移植までは、当たり前にスムーズに進むもの」
と思ってしまう方も多いのですが、実はそうとは限りません。
5年後、30代後半になると、
そもそも採卵ができない。
1個、2個しか卵が取れない。
受精しない。
移植までたどり着かない。
これまでスムーズにできていたところまでの道のりが、
一気に長くなってしまうこともあるのです。
だからこそ、「今」を大切に、進んでほしいと思います。
30代後半から40代の決断
この年代になると、「保険適応」との兼ね合いが、とても大きなテーマになります。
私は、
30代は移植6回、
40代は移植3回、
という現在の保険適応の考え方は、本末転倒だと感じています。
とはいえ、現実は厳しいものがあります。
そのため私は、場合によっては自費での採卵を組み合わせることを、お勧めすることもあります。
年齢を重ねると、卵巣の状態はアップダウンが大きくなります。
もし40代で、
もしその妊活が一人目の妊活であるならば、
「凍結は、時間を買うもの」
そう考えて、自費の採卵を組み合わせるという選択も、十分アリだと思います。
私は、「凍結とは時間を買う技術」だと考えています。
現在の保険適応の治療には、この発想があまりないように感じます。
もし卵巣機能が厳しくなってきたと感じたら、
ぜひこの考え方を、選択肢のひとつとして取り入れてみてください。
40代半ばの妊活について
40代半ばの方の妊活で大切なのは、
「今の状況を正しく把握すること」と、
「時間を大事にすること」。
私は、体外受精は時間を買う、ほぼ唯一の選択肢だと思っています。
もし、これまで一度も妊娠した経験がないのであれば、
ここは迷わず、採卵を行い、凍結胚を作ることをお勧めします。
保険適応で「6回まで移植できる」というのは、
裏を返せば、30代であっても
それくらい移植を重ねなければ、
妊娠・出産にたどり着かないケースが多い、ということでもあります。
だからこそ、
複数回の移植分を先に採卵・凍結しておくことが、何より大切。
そのうえで、移植に向けて必要なことを考えていく。
この順番が、とても重要だと思います。
40代半ば、自然妊娠への挑戦
あると思います。
40代半ばでの自然妊娠・出産。
これまでの経験から見ても、
「珍しいこと」ではなく、「確かにあること」だと感じています。
ただし、やはり条件はあります。
・男性側の状態に問題がないこと
・定期的な排卵があること
・子宮や卵巣を中心に、気血の巡りがよいこと
40代でも、妊娠はします。
ただし、その妊娠が出産までたどり着く確率は、
10代・20代とは違うということ。
そこには、やはり覚悟が必要です。
「惜しい」と感じることが多い、不妊カウンセリング
不妊カウンセリングをしていて、
「惜しいな」と感じるのは、
ネガティブな情報にフォーカスしすぎて、
前向きな選択ができなくなってしまっている方がいらっしゃることです。
また、情報を調べすぎるあまり、
ご自身の状況を踏まえた選択ができていないのでは、
と感じることもあります。
妊活は、ほんの少しのボタンの掛け違いで、
前に進まなくなることが多いものです。
もし、自分ひとりでは整理できないと感じたら、
生殖医療の「治療そのもの」から少し距離を置いた場所で、
視野を広げて相談してみることをお勧めします。
ただし、生殖医療を完全に否定するタイプの意見をもらってしまうと、
かえって混乱してしまうこともあるので、注意が必要です。
ご自身にとって、最善の道を選ぶことができますように。
そして、ほんの少しでも「子どもが欲しい」と思った方に、
良いご縁がありますように。