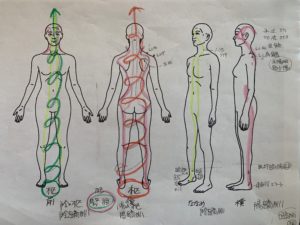子どもを持つ持たない問題
スティーブンジョブスの有名なスピーチ
この中に、コネクティングドットというのがあります。
何かを考えるときに、未来なんてわからない。
いま、自分が好きなこと、やりたいことをして、点を精一杯生きる
そしていつか振り返ると、その点がつながって、面白い未来になっていたと。
ジョブスは、大学を中退したあと、自由になって学んだフォントがのちのちのアップルコンピューターで花開いたという話しをしています。カリグラフィーフォントを学んでいたそのときは、ただただ興味深いものだった。将来にそれが役立つなんて思わなかったけど、後から振り返り、大学を中退したこと、カリグラフィーを学んだことはとってもよかったと振り返っているという話しです。
子どもを持つ持たない問題
子どもを持つ持たない問題を聞いていると、そんなところが重なります。
ときどき、ご夫婦の間で子どもを持つ持たない問題が一致しない方がいらっしゃります。
それはそれぞれの時間軸、価値を生きていれば当然生じてくることは理解出来ます。
子どもを持つ持たないのを、決めるのは荷が重すぎる
その上で、
夫婦としての今に、子どもをのぞむのか否か。
この問題は本来、「個人が決める」には大きすぎる問題です。
できれば、人生の流れの中で自然に訪れて、受け入れて、一緒に歩んでいけたらいいのかなと思います。
時間・年齢要因が女性にとってはとても厳しい
それでも決めなければならないとしたら、
子どもに関して女性には時間的な制約が多いという点は考慮したいですね。
一昔前は30才までに産み終えてなどという言葉がありました。
chatgpt先生に伺うと、最良の年代は20代前半、でも20代のウチは20%以上に妊娠率がアリ良好だと説明してくれています。
chatgpt先生のグラフから
30代をすぎるとガクッと妊娠率が落ちますね。
とにかく、年齢年齢・・・・・
だから、もし女性が子どもをのぞんでいるカップルの場合は
出来れば女性の意向を中心に考えてほしいなあって私は思ってしまいます。
人生の中の大きなドット
人生の中での大きな点。
そしてそのあとでは得ることの出来ない点
自分の子どもを得るというドットは、計り知れない大きさをもちます。もし、あなたのパートナーである女性がのぞんでいたとしたら、出来れば協力してあげてほしいなあなんて思います。


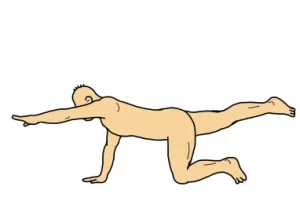 すぐ使えるリハビリのイラスト集さんから
すぐ使えるリハビリのイラスト集さんから