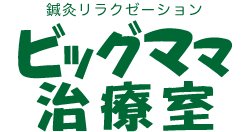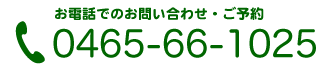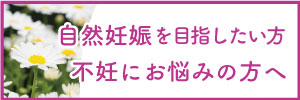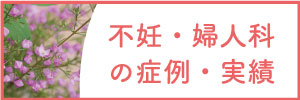(人間を樹木にたとえる生命観、養生の大切さ)
高円宮様がご逝去されましたね。その死は、まるで、大きな木が突然にばったりと倒れるような感じでした。
この少し前、40代の男性に、裏を起てる事、養生とはというテーマで文章を書きました。高円宮様の死を候って、まるでこの文章のイメージと同じだと思いました。
人の生き死には、我々の手の中にはなく、運命の糸に導かれているようにいつも思っています。
しかし、私は、いま、与えられているこの生命を、丁寧に大切にし、すこやかに過ごすことで、生命の時間の充実を、そしていま生きていることを楽しみたいと思っています。
以下の文章は、そのための養生につながるお話と思っていただいたら、いいのかなって思います。
****************************************************************
働き盛り、この年代は、非常に感覚を鋭敏にして、五感をフルに出動させている状態だと思います。
こういったときに、時に他の人から大丈夫?とか、気が張り詰めている感じや、ご自身でも大丈夫かな?身体はちょっと無理しているけど、なんか気持ちはハイだななどということがあるのではなでしょうか?
****************************************************************
人間を樹木にたとえることがあります。
大地に根をはり、天に向かって大きく枝葉を伸ばしている姿。どっしりとした根にささえられ、幹が天にむかってすこやかに伸び、枝葉が生い茂る、そんなイメージを生きている人間に対して私は持っています。
第一線にいて、枝葉をしっかり繁らせ感覚を鋭敏にとぎすまし、情報の海をわたるとき、人間は、少々無理をしても、気を張り、感覚を奮い起こします。根っこの状態がよければ、地上部は柔軟に動くことができます。
でも、根っこの状態が悪いのに、無理に頑張ろうとすると、木は、倒れないようにと、堅く、鎧をまとったように頑張ろうとします。
****************************************************************
肝が据わるという言葉があります。
個々のお体を拝見しなければ、現時点の状態が、時系列の中でどのような位置かが判然としないのですが、肝がすわるべき根っこがどーんとしていれば、他の人が?と心配するような雰囲気や、張り詰めた気の不安定さはあまりないと思います。感覚の鋭敏さがあっても、多分、そこには、どっしりとした安定感や、柔軟さを感じるでしょう。
これが、カルシウムを飲んだら?といわれるような状態だと、根っこの状態が落ちて来ているのに、無理に枝葉を張ろうとしているからだと、考えることが出来ます。スタミナドリンクの小ビンが手放せないのも同じですね。
これを続けると、ばったりと、木が幹が倒れるように倒れます。大きな木が、あるとき突然倒れる、そんなイメージでしょうか。男性はこのようなタイプの無理をしがちなのかとも思います。
また、お年寄りが頑固だと言われるのは、このような原理からです。気の張っていたときは元気だけど、それがとれたら、がっくりとくるというのは、こういったところから来ています。
年配の経営者が、柔軟な考えが出来ないなどと言われたり、病人は性格が悪くなるなどと言われたりするのも、裏(大地に根ざす根っこ)の状態が悪いのに、気を張り無理にがんばろうとする現れだと私は思っています。
****************************************************************
で、こういったときに、必要なのが、裏を立てる(根っこを充実させる)養生だと思います。イメージは臍下丹田の力をつけるです。足三里のお灸は手軽なので勧めることがよくありますが、他に、同じイメージを持つものならなんでも言いのです。
身体をふるに使っている、年代の方は、考えておいてもいいのではないかと、お節介ながら思いました。
裏をたてておくこと、中心を育てること、大地にどっしりと根をおろしたような体にすること。ある年代になったら、意識しておかなくてはならないのではと思います。